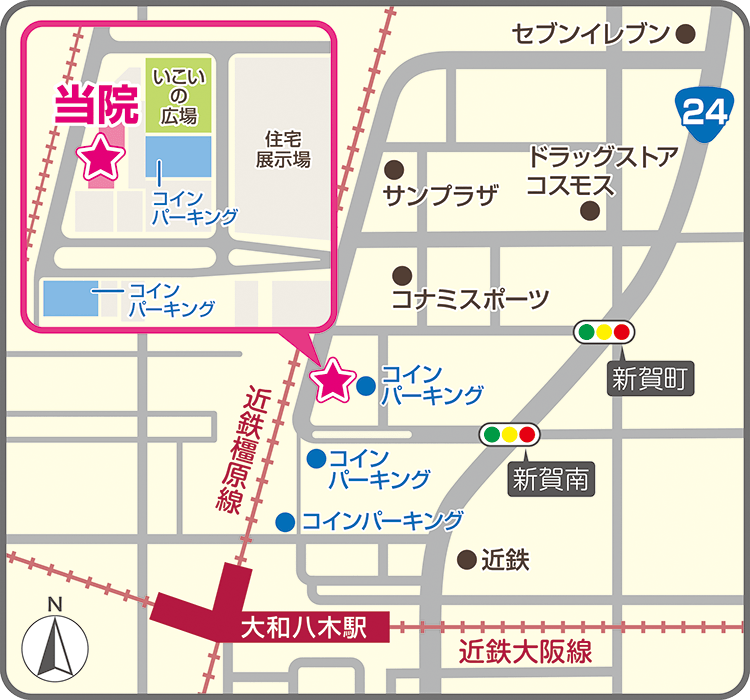狭心症とは
狭心症とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素と栄養を供給する冠動脈が狭くなり、血流が不足することで胸の痛みや圧迫感を引き起こす病気です。通常、冠動脈は心筋に十分な血液を供給していますが、動脈硬化などによって血管が狭くなると、運動やストレスなどで心臓が多くの血液を必要とする際に十分な血流が確保できず、症状が現れます。
狭心症は心筋梗塞の前触れとなることもあり、適切な治療を受けずに放置すると、心筋梗塞や突然死のリスクが高まります。症状が疑われる場合は、早めに医療機関を受診することが重要です。
狭心症の種類と原因
狭心症は主に「労作性狭心症」と「冠攣縮性狭心症(異型狭心症)」の2つに分けられます。
労作性狭心症
運動やストレスなどによって心臓の負担が増えたときに症状が現れます。
原因の多くは動脈硬化で、冠動脈の内側にコレステロールが蓄積し、血管が狭くなることで血流が滞り、発症します。
動脈硬化は加齢や高血圧、糖尿病、脂質異常症、喫煙、肥満などが関係しており、日頃の生活習慣が大きな影響を与えます。
冠攣縮性狭心症(異型狭心症)
冠動脈が一時的に強く収縮(けいれん)することで血流が遮断され、症状が現れるタイプの狭心症です。血管がもともと狭くなくても、収縮が起こることで血流が滞り、胸の痛みを引き起こします。
発症の原因として、喫煙や過度のストレス、寒冷刺激、アルコール摂取などが挙げられます。
狭心症の症状
狭心症の典型的な症状は、胸の中央部に生じる圧迫感や締めつけられるような痛みです。
多くの場合、痛みは数分から10分程度続き、安静にするか、ニトログリセリンを服用すると改善します。
労作性狭心症では、血管が狭くなっていることで、心筋に十分な酸素や栄養が供給されないことで発症します。
運動や階段の上り下りなどの身体活動時に、胸の中央付近に圧迫感や締め付けられるような痛みを感じるのが特徴です。痛みは通常数分間続き、安静にすると自然に治まります。症状が腕や首、背中に広がることもあります。
寒い場所での活動や精神的なストレスが引き金になることも少なくありません。
冠攣縮性狭心症は、安静時に突然胸の痛みが起こるのが特徴です。とくに夜間や早朝に発作が起こりやすく、睡眠中や目覚めたときに強い圧迫感や締め付けられるような痛みを感じることがあります。
痛みは数分から十数分続くことがあり、冷や汗や息苦しさを伴うこともあります。
冠動脈が一時的にけいれんし、血流が制限されることで発生し、血管の収縮が強くなると、心筋梗塞につながるリスクもあります。
胸の痛み以外にも、動悸、息切れ、肩や腕、首、あごへの放散痛(関連痛)を感じることがあります。
とくに糖尿病の患者様では神経障害により痛みを感じにくいため、違和感や息切れだけが症状として現れることがあります。
狭心症の危険性
狭心症が進行すると、軽い運動でも症状が出るようになり、次第に安静時にも発作が起こるようになります。これを「不安定狭心症」といい、心筋梗塞の前兆とされる危険な状態です。
不安定狭心症は、狭心症の中でもとくに注意が必要な状態で、心筋梗塞の前触れとして発症することがあります。
これまで安定していた狭心症の症状が悪化し、少しの運動でも強い胸の痛みが生じたり、安静時にも発作が起こったりするのが特徴です。
胸の圧迫感や締め付けられるような痛みが突然現れ、以前よりも長く続くことがあり、痛みが強まる場合もあります。
発作の頻度が増えることも多く、症状が治まりにくい場合もあります。これは冠動脈の動脈硬化が進行し、血流がさらに悪化しているサインであり、心筋梗塞に進行する危険性が高いため、早急にご受診ください。
狭心症の検査
狭心症の診断には、心電図検査が基本となります。安静時の心電図では異常が見つからないことも多いため、負荷心電図(運動負荷試験)を行い、運動時の心臓の変化を調べることもあります。
心臓超音波(心エコー)検査では、心臓の動きや血流の状態を確認し、心筋に異常がないかを評価します。
冠動脈CT検査は、冠動脈の狭窄の程度を詳細に調べるために有用で、動脈硬化の進行度を確認することができます。
さらに、確定診断のために冠動脈造影検査を行うことがあります。この検査ではカテーテルを血管に挿入し、造影剤を使って冠動脈の状態を詳しく調べます。
狭心症の治療法
狭心症の治療は、症状の程度や原因に応じて生活習慣の改善、薬物療法、カテーテル治療、外科手術が選択されます。
生活習慣の改善
狭心症の進行を防ぐための基本的な治療です。
食事の改善では、塩分や飽和脂肪酸の摂取を控え、野菜や魚を多く含むバランスの良い食事を心がけます。
さらに適度な運動を取り入れるほか、禁煙や節酒を行うことも大切です。
薬物療法
ニトログリセリンを用いて血管を拡張し、症状を軽減します。
さらに、β遮断薬やカルシウム拮抗薬を用いて心臓の負担を減らし、冠攣縮を抑えます。
また、動脈硬化の進行を防ぐために抗血小板薬やスタチン(脂質異常症治療薬)が処方されることもあります。
カテーテル治療(PCI)
狭窄した冠動脈を広げるためにバルーンを使って血管を拡張し、ステントと呼ばれる金属製の網状の筒を留置する治療法です。この治療により、血流が改善され、狭心症の症状が軽減されます。
冠動脈バイパス手術(CABG)
動脈の閉塞が重度で、カテーテル治療が適応にならない場合に行われます。
足や胸の血管を使って、新しい血流の通り道を作り、心筋への血流を確保します。