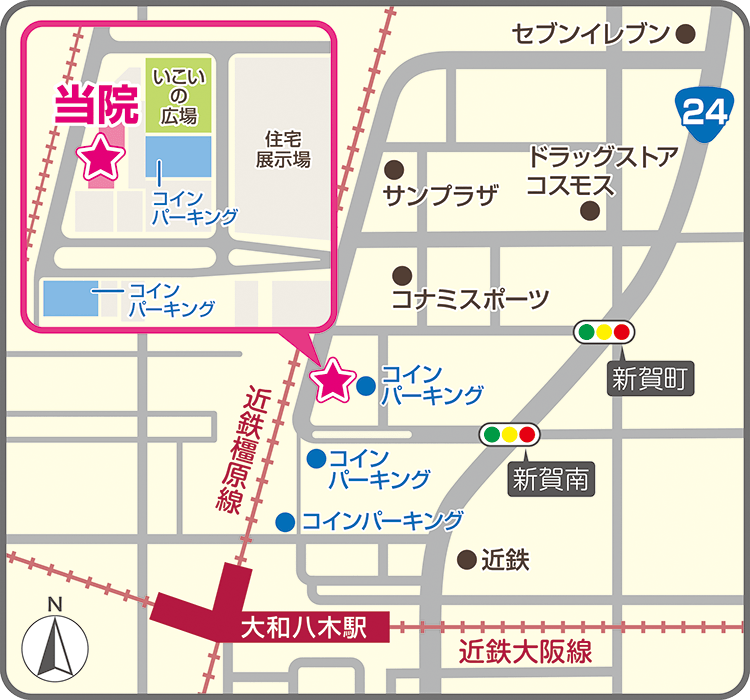心不全とは
心不全とは、心臓の機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなる状態を指します。
心臓は、酸素や栄養を含んだ血液を全身に送り出すポンプの役割を果たしていますが、その働きが弱くなると、全身の臓器や筋肉に十分な血液が行き渡らなくなります。
その結果、息切れやむくみ、疲れやすさなどの症状が現れ、日常生活に支障をきたすことがあります。
心不全は一つの病気ではなく、心臓のさまざまな疾患が進行した結果として生じる状態です。
放置すると徐々に悪化し、生命に関わる危険性があるため、早期の診断と適切な治療が重要になります。
なお、心不全には「慢性心不全」と「急性心不全」があり、それぞれ発症の仕方や症状の進み方が異なります。
慢性心不全は、心臓の機能が徐々に低下し、少しずつ症状が悪化する状態です。息切れやむくみ、疲れやすさなどが続き、生活の中で次第に動きづらくなります。
一方、急性心不全は、急性心筋梗塞や急性心筋炎など、なんらかのきっかけで突然心臓の働きが悪くなり、息苦しさや極度の倦怠感、むくみが急激に悪化する状態です。
重症になると命に関わるため、すぐに病院での治療が必要です。
また慢性心不全からも、急性心不全に移行する場合がありますので、こちらも要注意です。
心不全の原因となる主な疾患
心不全を引き起こす原因にはさまざまな心疾患や生活習慣病が関与します。
代表的な原因には、次のようなものがあります。
高血圧
血圧が慢性的に高い状態が続くと、心臓は強い圧力に耐えながら血液を送り出さなければなりません。
その結果、心臓の筋肉が厚くなり(肥大)、次第に柔軟性を失ってうまく収縮できなくなります。これが進行すると心不全へとつながります。
虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)
心臓の筋肉に酸素を供給する冠動脈が動脈硬化などで狭くなったり、詰まったりすると、心筋が十分な酸素を受け取れなくなります。狭心症は一時的な血流不足、心筋梗塞は血流が完全に途絶えて心筋が壊死する状態を指し、どちらも心臓のポンプ機能を低下させ、心不全を引き起こす原因となります。
心筋症
心筋症は心臓の筋肉そのものに異常が生じる病気で、心筋の収縮力が低下する拡張型心筋症や、心筋が過剰に厚くなり心臓の動きが制限される肥大型心筋症などがあります。
これらの病気は、心臓の働きを妨げ、心不全へと進行する可能性があります。
心臓弁膜症
心臓には血液の流れを調節する弁があり、これが正常に機能しないと血液が逆流したり、流れが阻害されたりします。
弁膜症が進行すると心臓に過度な負担がかかり、心不全を引き起こすことがあります。
不整脈
心臓のリズムが乱れる不整脈の中には、心臓の拍動が極端に速くなったり、遅くなったりするものがあります。
とくに心房細動などの不整脈は、血液の流れを悪くし、心不全の原因になることがあります。
心不全の症状
心不全では、心臓の働きが低下することで血液の流れが滞り、全身の臓器や組織に影響を及ぼします。症状の多くは、「うっ血」と「酸素供給の低下」によるものです。主な症状としては、以下のようなものがあります。
- 息切れ・呼吸困難
- 心臓が十分に血液を送り出せないと、肺に血液がたまり、肺の血管から水分が漏れ出します。これにより肺がうっ血し、呼吸が苦しくなります。とくに運動時や横になると症状が悪化するのが特徴です。重症化すると、夜間の就寝中に突然呼吸困難を感じることもあります。
- むくみ(浮腫)
- 心不全では全身の血液循環が悪くなり、とくに足の静脈に血液が滞留しやすくなります。その結果、足首やふくらはぎ、場合によっては全身にむくみが生じます。腎臓の機能も低下し、体内の水分を適切に排出できなくなることも原因の一つです。
- 倦怠感・疲れやすさ
- 心臓の機能低下により、全身の臓器や筋肉に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなります。そのため、日常生活の中で動くことが億劫になり、ちょっとした動作でも疲れやすくなります。
- 食欲不振・体重減少
- 血液の流れが悪くなることで消化管の働きが低下し、食欲不振や体重減少を引き起こすことがあります。これが進行すると「心臓悪液質」と呼ばれる状態になり、さらに全身の状態が悪化します。
心不全の危険性
心不全が進行すると、日常生活に大きな支障をきたし、最終的には命に関わる状態になります。
重度の心不全では、息切れが強まり、横になれず座っていないと呼吸が苦しくなることもあります(起坐呼吸)。
肺に大量の水分がたまり、急激に呼吸困難が悪化する「急性心不全」の状態になると、緊急治療が必要になります。最悪の場合、心臓が全く機能しなくなる「末期心不全」となり、心臓移植などの根本的な治療が必要になることもあります。
心不全の検査
心不全の診断には、症状の確認に加え、さまざまな検査を行います。
主な検査として、以下のようなものがあります。
- 心電図検査
- 不整脈や心筋梗塞の兆候を調べます。とくに、心臓のリズムの異常がある場合は、不整脈が心不全を引き起こしている可能性があります。
- 心エコー(心臓超音波)検査
- 心臓の動きや弁の状態を観察し、心不全の程度を評価するために有用です。心臓の収縮力や血流の異常を詳細に確認できます。
- 血液検査
- 血液検査では、心不全の影響による腎機能や肝機能の状況がチェックできるほか、とくに心臓の負担を示すBNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)の値を測定することで、心不全の有無や進行度合いを評価することができます。
- 胸部レントゲン検査
- 心臓の大きさや肺のうっ血の有無を確認し、心不全の診断を補助します。
心不全の治療
心不全の治療は、症状の進行を抑え、生活の質を向上させることを目的としています。
治療には次のような方法があります。
薬物療法
心不全の治療には、利尿薬(むくみを改善)、β遮断薬(心臓の負担を軽減)、ACE阻害薬やARB(血圧を下げ、心臓の負担を減らす)などの薬が使われます。
生活習慣の改善
塩分や水分の摂取量を調整し、適度な運動を取り入れることが重要です。
また、禁煙・禁酒も心不全の進行を防ぐために推奨されます。
デバイス治療
心不全が進行した場合、ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)、心臓再同期療法(CRT)などのデバイスを用いることがあります。
手術・カテーテル治療
重度の弁膜症や冠動脈疾患が原因の場合は、心臓手術やカテーテル治療が必要になることもあります。