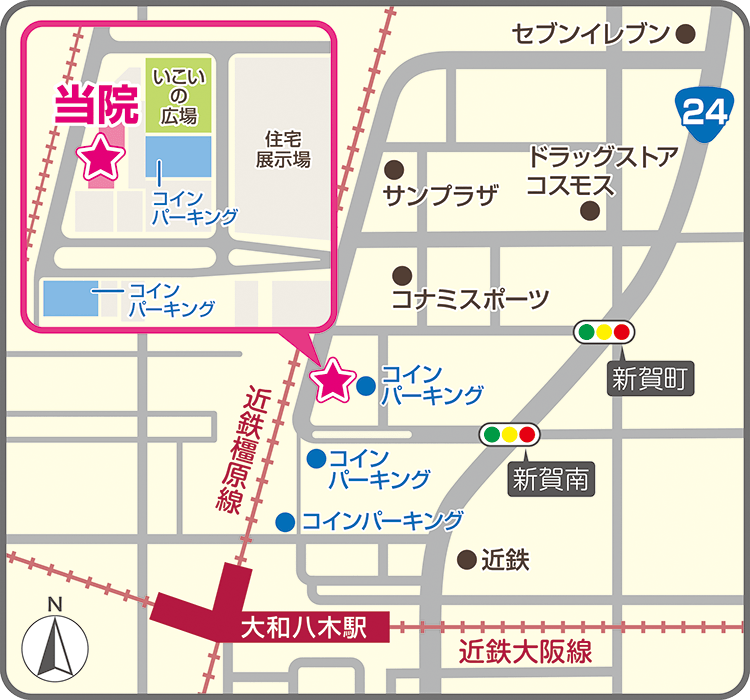不整脈とは
不整脈とは、心臓の鼓動が正常なリズムを維持できず、不規則になったり、異常に速くなったり、逆に遅くなったりする状態を指します。
通常、心臓は一定のリズムで収縮と拡張を繰り返し、全身に血液を送り出します。しかし、心臓を規則正しく動かすための電気信号に、何らかの理由で変化が生じるなどして不整脈が起こると、心臓のポンプ機能が乱れ、全身の血流に影響を及ぼすことがあります。
不整脈の多くは無症状のこともありますが、一部は動悸やめまい、失神などの症状を引き起こし、重症化すると心不全や突然死の原因となることもあります。そのため、気になる症状がある場合は、早めの検査と診断が重要です。
不整脈の種類
不整脈にはさまざまな種類があり、大きく分けると「頻脈性不整脈」「徐脈性不整脈」「期外収縮」に分類されます。
頻脈性不整脈
頻脈性不整脈とは、通常よりも心拍数が速くなる不整脈のことを指します。
通常、脈が1分間に100回以上の状態が続くものです。心臓の電気信号の異常によって心臓が正常に拍動しないことで、動悸や息切れ、めまい、胸の不快感などの症状が現れます。
要因としては、ストレス、電解質異常、心臓疾患などがあり、種類としては心房細動、心房粗動、発作性上室性頻拍、心室頻拍などがあります。
放置すると血栓や心不全のリスクが高まります。
徐脈性不整脈
脈性不整脈とは、通常よりも心拍数が遅くなる不整脈のことを指します。
健康な若い方やアスリートは心拍数が少ないこともしばしばあり、症状を伴わないことがあります。この場合、治療は必要ありません。
一般的には1分間の心拍数が60回未満だと徐脈とされ、50回未満になると、目の前が急に暗くなる、めまい、ふらつき、疲れやすさ、失神などの症状が現れることがあります。原因には加齢、心臓の病気、甲状腺機能低下、薬の影響などが挙げられます。重症の場合は、心臓が十分な血液を送り出せず、意識を失うこともあります。
期外収縮
期外収縮とは、心臓の通常のリズムとは異なるタイミングで発生する余分な拍動です。
主な症状は「脈が飛ぶ」「ドキッとする」「鼓動が乱れる」などの違和感ですが、多くの場合、一時的で健康な人にも見られます。
原因としては、ストレス、疲労、睡眠不足、カフェインやアルコールの摂取、喫煙、自律神経の乱れなどが挙げられます。また、高血圧や心疾患が関与することも少なくありません。
頻繁に起こる場合や、ほかの不整脈と合併している場合、めまい・息切れを伴う場合は注意が必要です。
不整脈の危険性
不整脈を放置すると、症状が悪化するだけでなく、脳梗塞や心不全などの重大な合併症を引き起こす可能性があります。
心房細動が長期間続くと、血液の流れが滞り、心房内に血栓ができやすくなります。この血栓が血流に乗って脳の血管を塞ぐと、脳梗塞を発症する危険があります。
心室からの異常な電気信号で脈が速くなる心室頻拍や、心室が痙攣している状態の心室細動は、突然死の原因となることがあり、緊急の対応が必要です。
これらは、心筋梗塞や肥大型心筋症、拡張型心筋症などの心疾患によって引き起こされる場合があります。
徐脈性不整脈では、心拍数が極端に遅くなると、血流不足により失神や意識障害を引き起こすことがありますが、車の運転中や高所作業中などに発症すると非常に危険な場合もあり、適切な治療が必要です。
不整脈の検査
不整脈の診断には、心電図検査が基本となります。安静時に心電図で異常が見られない場合でも、24時間のホルター心電図を装着することで、発作的に起こる不整脈を検出できます。
音波による心エコー検査では、心臓の構造や機能に異常がないかを調べ、不整脈の原因となる心疾患がないかを確認します。運動負荷試験や電気生理学的検査(EPS)は、不整脈の種類や発生のメカニズムを詳細に調べるために行われることがあります。
不整脈の治療
不整脈の治療は、症状の程度や種類に応じて異なります。
生活習慣の改善
軽度の不整脈で症状がない場合は、経過観察を行いながら生活習慣の改善を進めます。ストレス管理や適度な運動、カフェインやアルコールの摂取制限が効果的な場合もあります。
薬物療法
抗不整脈薬を使用し、異常な電気信号を抑えることで症状を軽減します。心房細動では、血栓予防のために抗凝固薬を併用することもあります。
ペースメーカー
徐脈性不整脈などで使用が検討されます。一定レベルの心拍を保ち、安定させることを目的とします。
植え込み型除細動器(ICD)
突発的な心室細動などが起きた際にも対応できるように埋め込むもので、危険な不整脈を検出し、電気ショックで正常なリズムに戻す役割を果たします。
カテーテルアブレーション(心筋焼灼術)
不整脈の発生源を特定し、高周波エネルギーで異常な電気回路を焼灼する治療法です。とくに心房細動や上室性頻拍の治療に有効とされています。
当クリニックでは、患者様の不整脈の管理をしていくとともに、上記のような治療が必要と判断した場合は、連携する専門の医療機関をご紹介いたします。