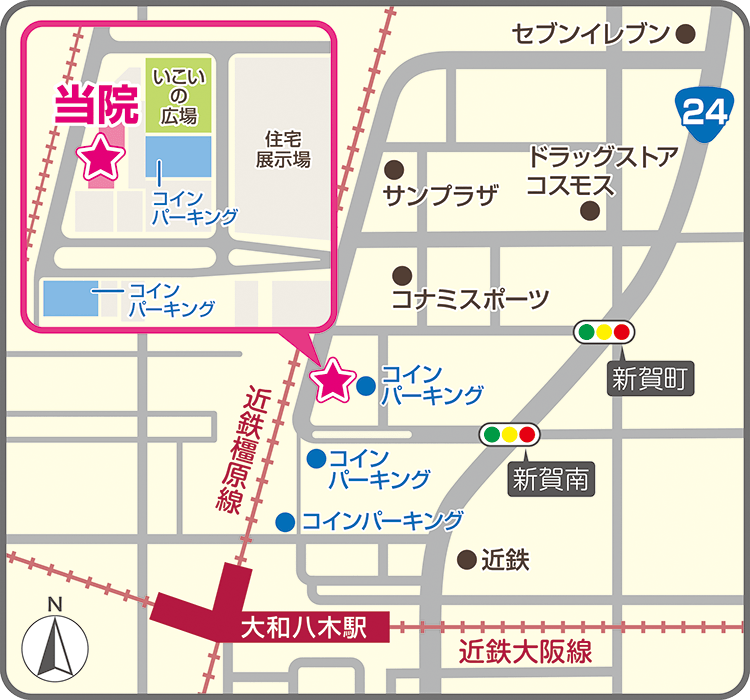動脈硬化とは
動脈硬化とは、血管が硬くなったり狭くなったりすることで、血液の流れが悪くなり、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患につながる病気です。
健康な動脈は弾力があり、血液をスムーズに送り出す働きを持っていますが、加齢や生活習慣の影響で血管の内側に脂質などが沈着し、血管の柔軟性が失われていきます。これが進行すると血管が狭くなり、血流が滞ったり、血管が詰まったりしてしまいます。
そうすると心臓や脳、手足などの臓器や組織への血液供給が妨げられ、さまざまな疾患を引き起こします。
動脈硬化は加齢とともに誰にでも起こる現象ですが、不適切な食生活や運動不足、喫煙などの生活習慣の影響を受けやすく、これらの要因によって進行が加速します。早期の段階では自覚症状がほとんどなく、気づかないうちに進行し、突然重度な合併症(脳梗塞や心筋梗塞 など)が発症することが少なくありません。
そのため定期的な健康診断でリスクを把握するなどし、適切な対策を取ることが大切です。
動脈硬化の種類と特徴
動脈硬化にはいくつかのタイプがあり、それぞれ原因や発症する部位が異なります。
アテローム硬化(粥状硬化)
最も一般的な動脈硬化のタイプで、主に大動脈や冠動脈、脳動脈などの中~大動脈に発生します。
血管の内壁にコレステロールなどの脂質が蓄積し、プラークと呼ばれる塊を形成します。これが進行すると血管が狭くなり、血流が低下します。
プラークが破れると血栓(血の塊)ができ、血管が詰まりやすくなり、心筋梗塞や脳梗塞を引き起こす原因になります。
- 主な原因
- 脂質異常症(高コレステロール)、高血圧、糖尿病、喫煙、肥満など
中膜硬化(メンケベルグ型硬化)
動脈の中膜と呼ばれる層にカルシウムが沈着(石灰化)することで起こります。とくに大動脈および足や頚部の動脈に多く見られ、高齢者に多いタイプの動脈硬化です。
血管が硬くもろくなり、血管壁が破れてしまうこともあります。進行すると末梢動脈疾患などのリスクを高めます。
- 主な原因
- 加齢、喫煙、高血圧、糖尿病、慢性腎臓病、ストレス など
細動脈硬化
細い血管(細動脈)が硬くなることで、血流が悪くなり、とくに脳や腎臓などの微小血管に影響を与えます。慢性的な高血圧が主な原因となり、血管壁が厚くなることで血液の流れが阻害されます。
進行すると血管が詰まったり血管の壁が破裂して出血したりし、脳出血や腎不全などを引き起こす可能性があります。
- 主な原因
- 高血圧、糖尿病 など
動脈硬化が原因となる症状・疾患
動脈硬化自体の初期段階では、自覚症状がほとんどありません。血管が徐々に狭窄したとしても、一定の血流が維持されるため、明確な症状が出ないことが多いのです。しかし、血管の狭窄が進行すると、血流が滞ることにより、さまざまな症状が現れるようになります。
動脈硬化の促進で引き起こされる疾患例としては、以下のようなものがあります。
狭心症
冠動脈が狭くなり、血流が一時的に不足することで胸の痛みや息切れが生じる病気です。
動脈硬化が原因で発症し、放置すると心筋梗塞に移行することがあります。
心筋梗塞
冠動脈が完全に詰まり、心筋が壊死する病気です。急激な胸の痛みや冷や汗、吐き気を伴い、迅速な治療が必要です。
末梢動脈疾患(PAD)
主に下肢の血管が狭くなり、歩行時の痛みやしびれが生じる病気です。進行すると足の血流が極端に不足し、間欠性跛行が生じ、壊死や足の切断が必要になることもあります。
大動脈瘤・大動脈解離
大動脈瘤は、大動脈の壁が動脈硬化などによって弱くなり、異常に膨らむ疾患です。破裂すると致命的な大出血を引き起こします。
一方、大動脈解離は、大動脈の内膜に亀裂が生じ、血液が壁の層の間に流れ込んで剥がれる状態を指します。急激な激しい胸や背中の痛みが特徴で、重症化すると生命に関わる危険な疾患です。
脳梗塞
脳の血管が詰まり、脳組織が酸素不足になることで発症します。障害される部位によって、言語障害や半身麻痺、意識障害などを引き起こし、重篤な後遺症が残ることもあります。
腎硬化症
動脈硬化によって腎臓の細い血管が狭くなり、血流が低下することで腎機能が徐々に低下する疾患で、むくみや尿の異常が生じます。とくに高血圧が原因となることが多く、進行すると腎不全に至ることもあります。
動脈硬化の改善法
動脈硬化は、一度進行してしまうと、残念ながら元に戻すのは難しい疾患です。
しかし、きちんとした対策をとれば、進行を遅らせ、重大な疾患につながることを、防ぐのも可能です。
動脈硬化を予防し、改善するためには、生活習慣の見直しが欠かせません。
まず、食事の改善が不可欠です。塩分や飽和脂肪酸を摂り過ぎないようにし、野菜や魚、大豆製品を多く取り入れることで、血圧やコレステロールを適正に保つことを目指します。また、糖質の過剰摂取を避け、適度なカロリーコントロールを心がけることも大切です。
運動習慣を身につけることも重要です。ウォーキングや軽いジョギング、水泳などの有酸素運動を継続すると、血管が柔軟になり、血流が改善されます。無理のない範囲で、週に3~5回、30分程度の運動を続けましょう。
さらに、禁煙と節酒も大きなポイントです。喫煙は血管を直接傷つけ、動脈硬化を加速させます。アルコールも過剰摂取すると血圧上昇を招くため、適量を守ることが大切です。
動脈硬化が進行している場合、薬物療法が必要になることもあります。
高血圧には降圧薬、脂質異常症にはスタチンなどのコレステロール低下薬、糖尿病には血糖コントロール薬が処方されることがあります。また抗血小板薬を用いて血栓の形成を防ぐ場合もあります。
動脈硬化は、血管が狭くなり、血流が悪化することでさまざまな病気を引き起こします。
そこで、生活習慣の改善や適切な治療を行うことが、進行を抑えることにつながり、心臓や脳の病気のリスクを減らす鍵となります。
動脈硬化の疑いがある場合は放置せず、まずは一度、お気軽にご相談ください。