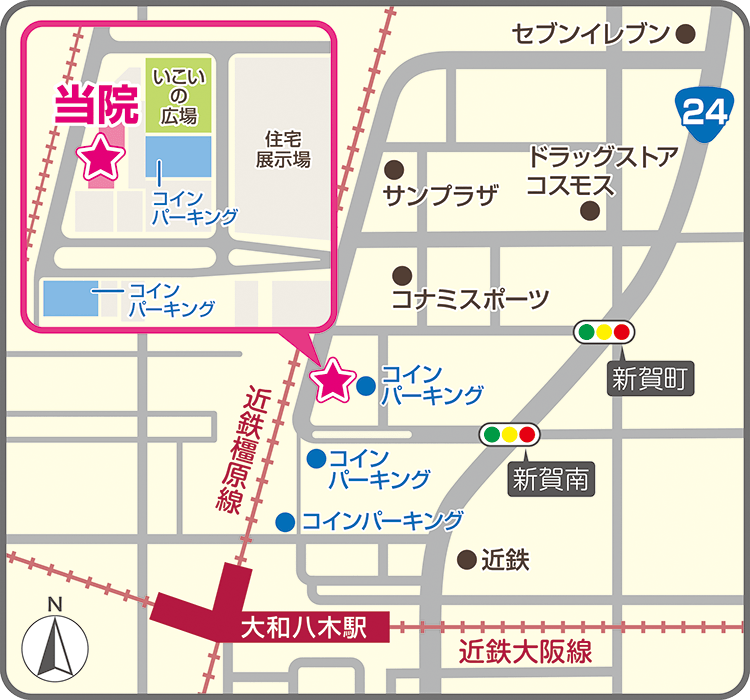心筋梗塞とは
心筋梗塞とは、心臓の筋肉(心筋)に酸素と栄養を供給する冠動脈が詰まり、血流が途絶えることで心筋が壊死してしまう病気です。
心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を果たしていますが、その働きを支える心筋が血流を失うと、短時間のうちに深刻なダメージを受けます。適切な対応が遅れると命に関わるため、迅速な治療が必要です。
心筋梗塞の原因
心筋梗塞は、多くの場合、動脈硬化が進行することによって発症します。
動脈硬化とは、血管の内側にコレステロールなどが蓄積し、プラークと呼ばれる塊ができる状態です。このプラークが破れると、血栓(血の塊)ができる場合があり、血管を完全に塞いでしまうことがあります。
血管が詰まると、その先の心筋に血液が届かなくなり、酸素不足の状態に陥ります。
これが心筋梗塞の発症原因となります。
心筋梗塞を引き起こす動脈硬化には、生活習慣病が大きく関与しています。
とくに高血圧や脂質異常症、糖尿病は、血管を傷つけ、動脈硬化を加速させるため、心筋梗塞のリスクを高めます。
こうした生活習慣病につながる運動不足や肥満、過剰なストレス、過度の飲酒もリスクを高める要因となります。喫煙も血管を収縮させ、血液を固まりやすくするため、大きな危険因子の一つです。
加齢とともに血管は硬くなるため、年齢も発症に関係し、とくに50歳以上の男性や、動脈硬化を抑制する女性ホルモンが減少する閉経後の女性は、注意が必要です。
心筋梗塞の主な症状
心筋梗塞の代表的な症状は、強い胸の痛みです。突然、胸の中央や左側に圧迫されるような激しい痛みが生じ、多くの場合、20分以上持続します。痛みが腕や肩、首、あご、背中に放散することもあります。なかには歯の痛みと思っていたら心筋梗塞だった、ということもあるため、要注意です。
胸の痛み以外にも、冷や汗や吐き気、呼吸困難、強い不安感を伴うことがあります。
とくに高齢者や糖尿病の患者様では、典型的な胸痛が現れず、息苦しさや倦怠感、めまいなどの症状が主になることがあります。このため、普段と違う強い違和感を覚えた場合は、心筋梗塞が疑われます。
心筋梗塞が疑われたら
心筋梗塞が疑われたら、一刻も早く医療機関を受診することが重要です。
場合によっては、ただちに救急車を呼びましょう。
救急車を待つ間は、血流を助けるために、上半身を少し高くして安静にしていましょう。
発症から治療までの時間が短いほど、心筋へのダメージを軽減できます。
心筋梗塞の治療法
心筋梗塞の治療では、詰まった冠動脈を早急に再開通させることが最も重要です。
そのため、以下の治療が行われます。
冠動脈カテーテル治療(PCI)
カテーテルを足や腕の血管から挿入し、詰まった血管を広げる治療法です。
バルーン(風船)を用いて血管を拡張し、ステントと呼ばれる金属製の筒を留置することで、血流を回復させます。
心筋梗塞の治療として最も一般的で、発症から早期に行うことで心筋のダメージを最小限に抑えることができます。
薬物療法
血液を固まりにくくする抗血小板薬、血栓を溶かす血栓溶解薬、心臓の負担を軽減するβ遮断薬やACE阻害薬などが使用されます。これらの薬は、再発予防や心機能の維持にも重要です。
冠動脈バイパス手術(CABG)
動脈の閉塞が重度であり、カテーテル治療では十分な効果が得られない場合に行われる手術です。
足や胸の血管を用いて、新しい血流の通り道(バイパス)を作ることで、心筋への血流を確保します。
予防と生活習慣の改善
発症すると命に関わる心筋梗塞は、予防すること、再発のリスクを軽減することが非常に大切です。
そのためには、生活習慣の改善が不可欠です。内容としてはバランスの取れた食事を心がけ、塩分や飽和脂肪酸の摂取を控え、野菜や魚を多く含む食事を意識することが重要です。
また適度な運動を習慣づけることで、血管の健康を維持し、肥満や糖尿病、高血圧の予防につながります。ただし、患者様の状態によっては危険もあるため、必ず医師の指示に従って行うようにしてください。
禁煙も心筋梗塞の予防には欠かせません。タバコは動脈硬化を促進し、血液を固まりやすくするため、完全に禁煙することが望まれます。
アルコールも適量を守り、過剰な飲酒を控えることが大切です。
ストレス管理も重要で、過度なストレスは血圧を上昇させ、心臓に負担をかけます。
十分な睡眠を確保し、リラックスする時間を持つことが健康維持につながります。