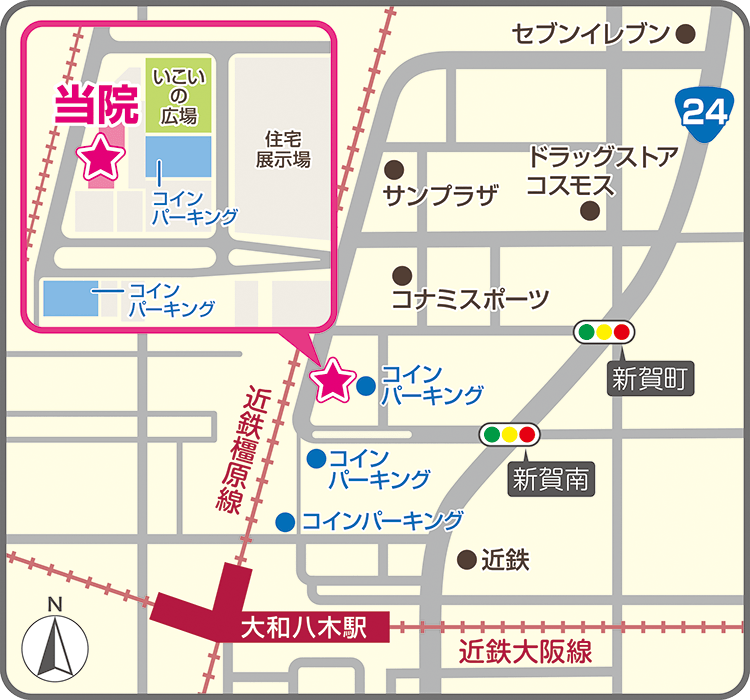心臓弁膜症とは
心臓弁膜症とは、心臓にある弁が正常に機能しなくなる病気です。
心臓には4つの弁(大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁)があり、それぞれ血液が適切な方向に流れるように開閉する役割を担っています。しかし、これらの弁が硬くなって開きにくくなったり(狭窄症)、閉じきらずに血液が逆流したり(閉鎖不全症)すると、心臓に負担がかかり、全身の血流が悪くなります。
心臓弁膜症は初期には自覚症状が少なく、気づかないうちに進行することが多い病気です。
放置すると心臓に過度な負担がかかり続け、心不全や不整脈、血栓による脳梗塞などを引き起こす可能性があるため、早期発見と適切な治療が重要です。
心臓弁膜症が引き起こされる原因
心臓弁膜症の原因はさまざまですが、加齢による変性が最も一般的です。年齢とともに動脈硬化などが原因で弁が硬くなったり、石灰化したりすることで弁の開閉が正常に行えなくなります。
また、子供の頃にかかったリウマチ熱の後遺症として弁が変形することもあります。リウマチ熱にかかると、その後ゆっくりと弁の変性が進行していき、何十年も経過したあとに心臓弁膜症を発症する場合があります。
先天的な異常として、生まれつき弁の形が正常でない場合もあります。例えば、大動脈弁は通常3つの弁尖で構成されていますが、一部の人では2つしかない(二尖弁)ことがあり、加齢とともに狭窄症を起こしやすくなります。
心臓弁膜症の種類
心臓弁膜症は、弁の機能異常によって「狭窄症」と「閉鎖不全症」に分類されます。
狭窄症は、弁が硬くなって開きにくくなることで血液の流れが制限され、心臓が過剰な負担を強いられる状態です。代表的なものに「大動脈弁狭窄症」や「僧帽弁狭窄症」があります。
閉鎖不全症は、弁が完全に閉じなくなり、血液が逆流する状態です。これにより心臓の負担が増加し、心不全のリスクが高まります。「僧帽弁閉鎖不全症」や「大動脈弁閉鎖不全症」がよく見られるタイプです。
心臓弁膜症の症状
初期の心臓弁膜症は無症状のことが多く、病気が進行するにつれて症状が現れます。
代表的な症状として、息切れや動悸が挙げられます。
階段の上り下りや軽い運動で息が切れる、横になると息苦しくなるといった症状が出ることがあります。
疲れやすさや倦怠感も特徴的な症状です。
心臓の機能が低下することで全身への血流が不足し、酸素や栄養が供給されにくくなって、体が疲れやすくなります。
むくみや体重増加も心臓弁膜症のサインです。
血液の循環が悪くなり、足や顔にむくみが現れ、短期間で体重が増えることがあります。重症化すると、めまいや失神を起こすことがあります。とくに大動脈弁狭窄症では脳への血流が減少することで意識を失うことがあるため注意が必要です。
心臓弁膜症の危険性
心臓弁膜症が進行すると、心臓にかかる負担が増し、心不全を引き起こす可能性があります。
心不全が進行すると、息切れが悪化し、日常生活に支障をきたすようになります。
また、弁の異常によって血流が乱れると、血栓が形成されやすくなり、脳梗塞のリスクが高まります。
とくに心房細動を合併した場合は、血栓が脳の血管を詰まらせる可能性があるため注意が必要です。
さらに、弁の機能が著しく低下すると、心臓のポンプ機能が破綻し、命に関わる状態になることもあります。
心臓弁膜症によって心臓内で血液の逆流が起きると、感染性心内膜炎を発症する場合があります。
これは、血液中から心臓に至った細菌が心臓内で繁殖することで起きます。
細菌が弁に付着して増殖すると弁が破壊され、急激に重度な心不全を引き起こし、命に関わることも少なくありません。
心臓弁膜症の検査
心臓弁膜症の診断には、いくつかの検査が行われます。
- 聴診
- 心臓の雑音(心雑音)の有無を確認します。
異常が疑われた場合、さらに詳しい検査を行います。 - 心エコー検査(超音波検査)
- 心臓の構造や弁の動きを詳細に観察できるため、弁膜症の診断に最も重要な検査です。
- 心電図検査
- 不整脈の有無や心臓の負担の程度を確認します。
- 胸部X線検査
- 心臓の大きさや肺のうっ血の有無を調べます。
- 運動負荷試験
- 心臓に負担をかけた状態での血流や心機能を評価するために行われることがあります。
心臓弁膜症の治療
心臓弁膜症の治療は、病気の進行度や症状の有無によって異なります。
軽症の場合は、定期的な検査を行いながら経過を観察し、生活習慣の改善を行います。
適度な運動、塩分制限、血圧管理が重要です。
薬物療法としては、心臓の負担を軽減するために利尿薬や降圧薬、抗不整脈薬、血栓予防のための抗凝固薬などが使用されます。
重症の場合や症状が進行した場合は、外科的治療が必要になります。
代表的な手術には、自身の組織で新たな弁をつくり、修復する弁形成術や、人工弁と交換する弁置換術があります。
最近では、開胸手術を行わずにカテーテルを用いて狭くなった弁をバルーン(風船)で膨らませるものや、新たな弁を留置するTAVI(経カテーテル的大動脈弁置換術)など、低侵襲治療も選択肢として増えてきています。