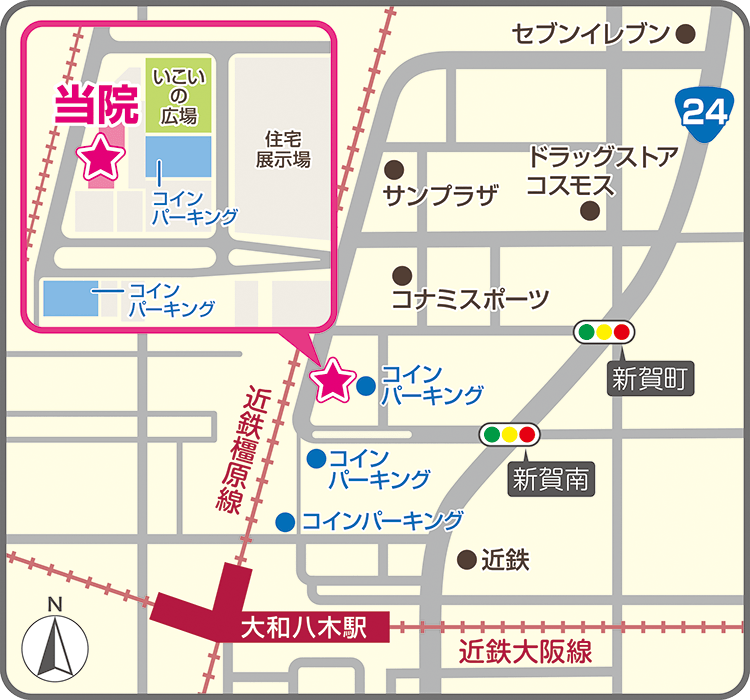高血圧とは
高血圧とは、血圧が慢性的に正常範囲を超えて高くなっている状態を指します。
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に血管壁にかかる圧力のことです。正常な血圧はおおよそ収縮期血圧(上の血圧)が120mmHg未満、拡張期血圧(下の血圧)が80mmHg未満とされていますが、高血圧ではこれを超える状態が続きます。
日本高血圧学会の基準では、医療機関での診察室血圧が収縮期血圧140mmHg以上、または拡張期血圧90mmHg以上の場合、また家庭で測定した場合は収縮期血圧135mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上の場合に、高血圧と診断されます(一度の測定結果だけで判断せず、複数回の測定結果を基に診断します)。
高血圧は自覚症状が乏しいため、気づかないうちに進行し、放置すると脳や心臓、腎臓などに重大な影響を及ぼします。
適切な管理を行うことで、合併症のリスクを減らし、健康的な生活を維持することができます。
高血圧の種類と原因
高血圧には大きく分けて「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の2種類があります。
本態性高血圧
原因が特定できない高血圧で、高血圧の患者様の約90%を占めます。
加齢や遺伝的要因のほか、塩分の摂取過多、運動不足、肥満、ストレス、喫煙、過度の飲酒などの生活習慣が関係していると考えられています。
二次性高血圧
特定の病気が原因で血圧が高くなる状態です。
腎臓病やホルモン異常、睡眠時無呼吸症候群などが関与しており、原因となる病気を治療することで血圧が改善する場合があります。
高血圧の症状
高血圧は「サイレントキラー」とも呼ばれるほど、初期にはほとんど自覚症状がありません。
しかし、血圧が高い状態が続くと、次のような症状が現れることがあります。
- 頭痛、とくに朝起きたときに頭痛がする
- 夜間に頻尿になった
- めまい、ふらつきがみられる
- 動悸や息切れがする
- 耳鳴りがする
- 肩こりが取れない
- 疲れやすい、集中力が低下する
など
ただし、これらの症状がなくても高血圧が進行している場合があるため、定期的に血圧を測定し、気になる場合はお気軽に当クリニックにご相談ください。
以下のような場合、お早めにご受診ください
- 家庭で血圧を測定し、135/85mmHg以上の値が続いている
- 健康診断で高血圧を指摘された
- 頭痛やめまい、動悸、息切れなどの症状が気になる
- 家族に高血圧や心筋梗塞、脳卒中の人がいる
- 高血圧の治療をしていたが、中断してしまっている
など
とくに健康診断で指摘された場合は、症状がなくても放置せず、早めの受診が大切です。
高血圧には以下のような疾患を引き起こすリスクがあります
高血圧を治療せずに放置すると、血管や心臓に大きな負担がかかり、以下のような、さまざまな合併症を引き起こす危険があるため、適切な管理が必要になります。
脳卒中(脳出血・脳梗塞 など)
高い血圧が続くと脳の血管が破れたり、詰まったりして脳卒中のリスクが高まります。
心筋梗塞・狭心症
心臓の血管が動脈硬化を起こし、血流が悪くなることで心筋梗塞や狭心症を引き起こします。
心不全
圧が高い状態が続くと、心臓に負担がかかり、心臓の機能が低下する心不全を発症することがあります。
腎臓病(慢性腎臓病・腎不全)
高血圧が続くと腎臓の血管が損傷し、腎機能が低下し、最悪の場合は透析が必要になることもあります。
大動脈瘤・大動脈解離
高血圧が原因で血管の壁が弱くなり、大動脈にコブができたり、血管が裂けたりする危険があります。
高血圧の治療
高血圧の治療の基本は、生活習慣の見直しです。
生活習慣の改善だけでは血圧が十分に下がらない場合、医師の判断により降圧薬などによる薬物療法を行います。
生活習慣の改善
- 塩分を控えた食事(1日6g未満を目標)を心がけます
- バランスの良い食事、とくに脂質を控え野菜を積極的に摂るようにします
- ウォーキングや軽い筋トレなど、適度な運動を習慣化するようにします
- 体重管理をし、肥満の解消に努めます
- 禁煙をし、アルコールも適量に抑えます
- 十分な睡眠をとり、リラックスできる時間を持つなど、ストレスを溜めないようにします
高血圧で処方される主な治療薬(降圧薬)
- カルシウム拮抗薬
- 血管を広げて血圧を下げます
- ACE阻害薬・ARB
- 血圧を上げるホルモンの働きを抑え、血圧を安定させます
- 利尿薬
- 体内の余分な水分や塩分を排出し、血圧を下げます
- β遮断薬
- 心拍数を抑えて血圧をコントロールします
- 薬は血圧の管理のために、長期間の服用が必要になることが多いため、自己判断で中止せず、医師の指示に従うことが大切です。